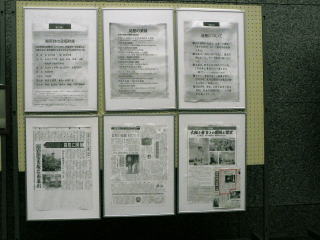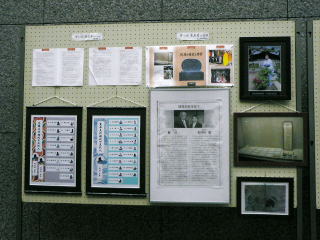対象
|
展示物 |
淀屋との関係 |
備考 |
第1回は、「淀屋の歴史と偉業」として、淀屋の栄枯盛衰と大坂に対する貢献の数々をご紹介しました。第2回は、「淀屋と文化人
|
そしてゆかりの人々」として、2代言当・4代重当を中心に松花堂昭乗、沢庵和尚をはじめの文化人の方々のスポンサ-でした。
|
また、大石内蔵助や水戸光圀との関係も深く、写真と関係をご紹介しました。第3回の今回は、「淀屋の信仰と神社・寺院そして
|
ゆかりの倉吉・八幡」として、淀屋の信仰と隠匿善事として石清水八幡宮・妙心寺・東大寺を始め多くの神社仏閣にたいする寄進
|
をしましたのでその一部をご紹介します。そして、倉吉は後期淀屋の発祥地であり、八幡は前期淀屋の最初と最後を観ています。
|
| 右側●淀屋について●淀屋の業績他●新山先生と1・2回の概要 左側●神社・寺院●倉吉・八幡・特別 |
| テ-マ |
信仰と神社・寺院 |
淀屋は歴代信仰に厚いが、膨大な寄進は隠匿善事でした。
|
|
| 倉吉との関係 |
闕所になる前に淀屋の暖簾をだし、59年後大坂にも。
|
|
| 八幡との関係 |
淀屋は八幡の神人。闕所後広当は八幡に隠遁し、建墓も。
|
|
●A1淀屋について
|
|
|
|
| |
淀屋について |
初代常安・2代言当は大坂の救世主でした。
|
|
|
淀屋の系図 |
淀屋は前期・岡本家と後期・牧田岡本家が明治直前まで。
|
|
|
淀屋の略(系)図 |
淀屋の歴史と偉業の一部をご紹介します。
|
|
|
淀屋と分家 |
それぞれの位置づけをご紹介します。
|
|
| ●A2淀屋の業績・財産 |
淀屋の業績は、大坂のみならずわが国への貢献も多大なものがあります。没収された財産も日本一でしょう。
|
| (右中) 淀屋と倉吉の関係 |
新聞の切り抜きをご紹介します。
|
| ●A3新山先生について |
作家であり、わが国第一の淀屋研究家です。27年にわたる調査・顕彰には頭が下がります。
|
| (右奥) 第1回・第2回図録 |
第1回の図録(左奥にも)と第2回の文化人とゆかりの人たちのご紹介です。
|
| 神社 |
|
守り神は弁財天・商売の神は若永神社でした。
|
|
| 淀屋の守り神 |
守り神は弁財天ですが、現在はありません。淀には弁財天祠が、東京冬木邸にも。
|
|
| 若永神社 |
若永神社 |
淀屋橋の邸内にありましたが、現在は大阪城内にあります。
|
|
|
立て札 |
神社の左側に建てられています。
|
|
|
邸内図面 |
2万坪の邸内に。図面上には48の蔵の位置づけも。
|
|
| 弁財天 |
弁財天の地図 |
江戸時代の絵図です。
|
|
| 辰五郎大明神 |
全景 |
奈良県三輪神社左奥の丘にあります。詳細は不詳。お守りは村上氏。
|
|
| |
祠 |
辰五郎大明神を真ん中に3社あります。
|
|
| |
鳥居 |
まだきれいでした。
|
|
| |
参道 |
お参りの方は結構あるとのことでした。商売の方が多いとか。
|
|
淀屋ゆかりの神社
|
|
|
|
| 石清水八幡宮 |
正面 |
昔から淀屋とゆかりの深い神宮で、昔は伊勢神宮と並び称せられたそうです。
|
|
| 大阪天満宮 |
正面 |
菅公750年忌の連歌興行に重当が件句しています。
|
|
| 住吉大社 |
正面 |
大坂町民の尊敬を集めており、広当も70日もおまいりしたとか。
|
|
| 佐太天神宮 |
正面 |
守口市にある神社で、元老中の永井尚政と姻戚の淀屋が大事にしました。
|
|
|
拝殿 |
4代重当が永井尚政の名前で1648年当主15歳に建立しました。
|
|
|
石井筒 |
父3代箇斎がなくなり、当主になって3年目の17歳に寄進しました。
|
|
|
棟札 |
拝殿の棟札です。表の左上の「淀屋右衛門太良尉」が重当です。
|
新発見 |
|
36歌仙 |
言当の甥乗円の書いた36歌仙の現物です。
|
|
|
献句 |
不明となっていた2代言当の弟道雲の子「専甫」も献句ししています。
|
専甫を発見 |
|
外壁 |
重当の修理したといわれる外垣です。
|
|
| 與杼神社 |
正面 |
淀の氏神として、現在は淀城の中にあります。
|
|
|
高灯篭 |
この高灯篭に次欄の文字が刻まれています。
|
|
|
刻印(右) |
「亭々欽寸輝」の文字
|
新発見 |
|
刻印(左) |
「灼々傳千古」の文字
|
新発見 |
|
新町八幡宮 |
淀町にある淀屋との関連がうかがえます。
|
|
| 福島天満宮 |
正面 |
福島駅の近くにある神社で4代重当が島津藩士4名と社殿を修復しました。
|
|
|
|
|
|
淀屋の菩提寺
|
|
|
|
| 大仙寺 |
|
元妙心寺住職竜岩和尚の建立で、淀屋岡本宗家の菩提寺です。
|
日円:妙福寺 |
| 願生寺 |
|
大仙寺の隣にあり、後期淀屋の淀屋清兵衛家の墓があります。
|
|
| 珊瑚寺 |
|
岡本家の分家の菩提寺です。
|
|
| 神応寺 |
|
淀屋とは昔から縁の深い寺ですが、広当が闕所後自ら建墓して旅へ?
|
|
| 大蓮寺 |
|
倉吉にある後期の牧田淀屋の菩提寺で、清兵衛家の墓もあります。
|
|
| C2 ゆかりの寺院 |
|
淀屋の隠匿善事は近畿一円の寺院に紫衣を配したとあります。
|
|
| 妙心寺 |
正面 |
臨済宗妙心寺派総本山で寺城48千坪、大仙寺の親寺です。
|
|
|
経蔵 |
2代言当が一切経蔵を寄進、4代重当は本格的な経蔵を寄進しました。 |
|
| 東大寺 |
正面 |
奈良の大仏やお水取りで有名な東大寺です。
|
|
|
2月堂梵鐘 |
重当は1668年、2月堂に梵鐘を寄進しました。序銘は妙心寺月詔和尚。
|
|
| ●D淀屋ゆかりの倉吉市 |
|
倉吉市は、重当が池田公の庇護のもとに造った後期牧田淀屋の町です。
|
|
| 牧田家の建物(現存) |
|
大坂に還る直前に建てた倉吉市最古の町屋です。現存はその一部。
|
|
|
全景 |
通りからみるとなんの変哲もありませんが、柱等内部はすごいそうです。
|
|
|
欄間 |
いつの頃のものかは不明です。
|
|
|
かまちの飾り
|
|
|
|
紋の入った瓦 |
牧田家の門の入った瓦ですが、大坂の願生寺のものと同じです。
|
|
| 対象 |
展示物 |
淀屋との関係
|
備考 |
|
牧田家の模型 |
第1回淀屋展で展示しましたが立派な模型です。大坂の本宅も
|
|
| 淀屋牧田家の菩提寺 |
|
牧田家の菩提寺で、ここの淀屋清兵衛の墓碑から後期淀屋が発見されました。
|
|
| 大蓮寺 |
正面 |
白壁土蔵群の一角にあります。
|
|
|
淀屋清兵衛家の墓 |
銘が刻んであります。
|
|
|
牧田家墓群 |
牧田家代々のお墓です。
|
|
|
厨子 |
淀屋清兵衛の寄進した厨子です。
|
|
| 蔵内牧田家の墓石群 |
|
鎌倉時代から続くという倉吉にある庄屋・大庄屋をしていた牧田家です。
|
|
|
墓群 |
古い時代のものからあります。淀屋との関係は不明です。
|
市誌未掲載 |
| 淀屋ゆかりの寺院 |
|
倉吉には淀屋ゆかりの寺院は沢山ありますが、関係の明確なものを。
|
|
| 長谷寺 |
本堂 |
倉吉の頭上になる打吹山の一角にあります。霊場です。
|
|
|
仏像 |
明現寺にあった坐像ですが、廃寺化とともに長谷寺に安置されています。
|
|
| 長伝寺 |
正面 |
昔酒田港とともに栄えた橋津にある寺院です。
|
|
| 南苑寺 |
正面 |
三朝温泉のホテル岩崎の裏にある無人寺で広当の絵が発見されました。
|
|
| 興宗寺 |
羅漢座像 |
橋津から近い青谷(現鳥取市)にある十六羅漢のうちの一体です。
|
3代清兵衛寄進 |
| 巖城寺 |
岩全景 |
山名氏の築城田内城跡の断崖に刻まれた「南無阿弥陀」です。
|
|
|
祈願者 |
9人の中に、牧田2代「淀屋孫三郎」の名があります。
|
|
ゆかりの神社
|
|
|
|
| 賀茂神社 |
正面 |
京都の上加茂神社と同系という賀茂神社です。
|
|
| 住吉神社 |
正面 |
賀茂神社の近くにあり、傍の礎石に淀屋の名も刻まれています。
|
|
淀屋ゆかりの鍛治町
|
|
|
|
|
街並み |
最盛期は1,000人の職人がいたという鍛治町です。
|
|
|
稲扱き千刃 |
重当が考案し、池田公の庇護で日本中に販売した倉吉製の千刃です。
|
パリ博に出品 |
| 倉吉の名跡 |
|
|
|
| 国府跡 |
全景①②③ |
ほうきの国の国府跡です。
|
|
|
南大門 |
法華寺の門です。
|
|
| 大岳院 |
正面 |
1605年創建の寺院です。元沼津城主中村公の菩提寺です。
|
|
|
大江磐代君墓所 |
第119代光格天皇のご生母はこの倉吉でお生まれになりました。
|
|
|
里見殉死者墓 |
元館山藩主里見氏は倉吉に転封されました。里見氏と殉死した8人の墓です。
|
|
| 白壁土蔵群 |
玉川のほとり |
西日本で行ってみたい白壁の町のNO5に入りました。
|
|
| ●E淀屋ゆかりの八幡市 |
|
八幡市は淀とともに淀屋と縁の深い街です。
|
|
| 石清水八幡宮 |
正面 |
淀屋は言当に次いで、4代重当も神人になりました。
|
|
|
鳥居 |
淀屋とは昔から縁の深い神宮です。大石良雄の弟・子も入山していました。
|
|
|
本殿 |
本殿は、家光の修復となっていますが、淀屋が負担したとあります。
|
|
| 神応寺 |
山門 |
神応寺も縁が深く、永井尚政も祀ってあります。
|
|
|
法要 |
昨年、16人の僧による闕所300年の法要が行われました。
|
|
|
扁額 |
淀屋寄進の額です。
|
|
|
淀屋の墓 |
2代言当や5代広当の墓もあります。
|
|
| 松花堂 |
草庵 |
松花堂昭乗の過ごした庵です。
|
|
|
茶室 |
沢山の文化人仲間が集まりました。
|
|
|
手水鉢 |
淀屋の別荘にあった「砧の手水鉢」です。
|
|
|
常勝寺 |
松花堂庭園に近く、言当の親交のあった松花堂昭乗が眠る寺です。
|
|
| 闕所後の広当 |
下村家と碑 |
闕所後、広当が下村こ庵と名乗り、住んだという屋敷の門と碑です。
|
|
|
水源 |
神応寺の山手にある水源で、ここから屋敷の手水鉢まで引いたそうです。
|
|
|
安居橋 |
水はこの橋の下を通ったといいます。安居祭りもありました。
|
|
|
ドントの辻 |
この辻を通って水は屋敷まで届いたといいます。
|
|
● 特 集 ●(図録の写しも添付しています)
|
|
|
| ○淀屋の仏壇 |
京都 |
世界の宝石をちりばめてあるという仏壇で、中には十字架が写るといいます。
|
|
| ○淀屋の持ち船の天井絵 |
円福寺 |
八幡の円福寺に牧田家ゆかりの方の寄贈とのことです。
|
最近の資料です |
本日はありがとうございました。これからも、大阪を元気にするために、偉大な先人たちの
|
ご紹介をしていきます。皆様のお力添えをお待ちしています。
|
*大阪・京都・奈良を拠点にしておられる団体・企業の方のご入会・ご支援をお待ちしています。
|
また、淀屋に関する情報をお知らせ下さい。特に屋敷内・家屋の間取り・中之島の730の米蔵資料を探しています。
|
●大阪を元気にする「淀屋研究会」へのご入会・お力添えをお待ちしています。
|
○住所 〒530-0001 大阪市北区梅田1-1-3-2200 大阪駅前ビル22階
|
倉吉市大阪事務所内 淀屋研究会事務局 伊藤 博章
|
○FAX・メ-ルで、団体名・氏名・住所・電話・FAX・Mアドレス・口数のご連絡を。
|
○TEL:06-6341-0170 FAX:06-6341-3972
|
○メ-ル: yodo-ken@ric.hi-ho.ne.jp
|
○HP 「淀屋研究会」「ヨドケン」で開きます。(今後のご案内はHPで)
|
○淀屋研究会 淀屋の真実と大阪に対する偉大な業績を顕彰します。 顧問:脇田修・新山通江先生
|
○淀屋研究会の会費
|
19年度会費案(年会費・通信費等)個人 3,000円 団体 12,000円
|
●第1回図録のご購入は「新風書房」まで(1,050円、第2回は無料
TEL:06-6768-4600 FAX:06-6768-4354
|
●今後の予定
|
|
|
|
●1月23・30・2月6日 大阪府:大阪文化再発見講座 「淀屋」に関する講座(有料)
|
講演 講師 童門冬二・新山通江・伊藤博章 (展示も23日~2月9日)さいかくホ-ル
|
●3月 第3回 淀屋サミット
|
●5月 第4回 淀屋展 「淀屋の偉業と没収された財産そして大坂・船場」 場所 未定
|




 12
12